こんにちは!温泉ソムリエの「モガミ」です!
さて、日本には数多くの温泉が存在していますが、実は温泉の泉質から周辺環境まで、何に注目するかを変えるだけで、それぞれが全く別物に見えてくるという面白さがあります。
今回は、温泉をあらゆる角度から分類する企画として、まずは「お湯」に注目した分類を行いたいと思います。温泉を楽しんだり、自分にあった温泉を探す際の参考にしていただければ幸いです。
※「環境編」も掲載しています。よろしければ、ご覧ください。
お湯に注目した分類
泉質(温泉に含まれる成分)
温泉は、国の法律により、含まれる成分によって10種の泉質に分類されており、それぞれに対応する効能が定められています。以下、その特徴とその泉質が持つ効能を順番に記述します。
(注)温泉の研究はまだまだ途上であり、以下の効能は絶対的なものではありません。効能を過信せず、また、症状の本格的な治療は専門医の助言のもとに行っていただくことをおすすめします。
参照元:温泉法に関する通知・ガイドライン等について [温泉の保護と利用]
単純温泉

含有成分の量がどれも一定値に達していない温泉です。
よく、成分が単純で温泉としての価値が小さいと誤解される傾向にありますが、「成分が薄い=やさしい泉質」のため、子供や高齢者、体力が弱った方にとっては最も入りやすい泉質の温泉です。また、成分が薄いとはいっても通常の入浴剤入りのお風呂以上の成分を含有しているものも多く、全国的に知られた下呂温泉(岐阜県)や道後温泉(愛媛県)、湯治場として有名な俵山温泉(山口県)などの名湯も単純温泉です。
効能としては、浴用では、自律神経不安定症、不眠症、うつ状態に良いとされています。
塩化物泉

海水の成分に似た食塩を多く含む温泉です。
入浴することで皮膚に塩分が付着し、汗の蒸発を防ぐことから、保温効果が高く湯冷めしにくい泉質であり、有名な温泉地としては、白浜温泉(和歌山県)、熱海温泉(静岡県)などがこちらに該当します。
効能としては、浴用では、きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症、飲用では、萎縮性胃炎、便秘に良いとされています。
炭酸水素塩泉

炭酸水素塩泉は、炭酸水素イオンを多く含む温泉です。
旧分類では、カルシウムかマグネシウムを多く含む「重炭酸土類泉」とナトリウムを多く含む「重曹泉」に分かれており、前者は皮膚の炎症に対する鎮静効果が、後者は皮膚の表面を軟化させる作用が期待できることから「美肌の湯」としての効果が期待されており、有名な温泉地としては、嬉野温泉(佐賀県)、強羅温泉(神奈川県)などがこちらに該当します。
効能としては、浴用では、きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症に、飲用では、胃十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、耐糖能異常(糖尿病)、高尿酸血症(痛風)に良いとされています。
硫酸塩泉

硫酸塩泉は硫酸塩を多く含む温泉です。
さらに、カルシウムを多く含む「石膏泉」、ナトリウムを多く含む「芒硝泉」、マグネシウムを多く含む「正苦味泉」に分けることができ、それぞれ効能に若干違いがあるとされていますが、鎮静作用など基本的に回復期にある外傷を治療中の方にとって嬉しい温泉であり、有名な温泉地としては、山中温泉(石川県)、山代温泉(石川県)、法師温泉(群馬県)が該当します。
効能としては、浴用では、きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症に、飲用では、胆道系機能障害、高コレステロール血症、便秘に良いとされています。
二酸化炭素泉

二酸化炭素(炭酸ガス)を多く含む温泉です。
泉温が高温すぎるとすぐに気化してしまうことから、レアな温泉であり、入浴すると肌にたくさんの気泡が付着することが大きな特徴です。有名な温泉としては、長湯温泉(大分県)、花山温泉(和歌山県)があります。
効能としては、浴用では、きりきず、末梢循環障害、冷え性、自律神経不安定症に、飲用では、胃腸機能低下に良いとされています。
含鉄泉

鉄分を多く含んだ温泉です。
元々のお湯は透明ですが、お湯の中の鉄分が空気に触れて酸化することで茶褐色になり、また、お湯からも強弱こそあれ鉄の匂いがするため、特別感のあるお湯を楽しむことができます。有名な温泉地としては、有馬温泉(兵庫県)、毒沢温泉(長野県)があります。
効能としては、飲用では、鉄欠乏性貧血に良いとされています。
酸性泉

名前のとおり酸性度が高い温泉です。
火山性の温泉に多く、抗菌力を有しており、個人的には大地のパワーを体で浴びているような感覚を得られるため、特に好きな泉質の1つである一方で、刺激が強い温泉として知られており、敏感肌、乾燥肌の人、赤ちゃん、高齢者などは注意が必要な泉質です。温泉地としては、草津温泉(群馬県)、万座温泉(群馬県)、蔵王温泉(山形県)、玉川温泉(秋田県)などが有名です。
効能としては、浴用では、アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、耐糖能異常(糖尿病)、表皮化膿症に良いとされています。
含よう素泉

うがい薬や傷薬で知られたヨウ素を多く含む温泉です。
平成26年の法律改定により、新たに追加された泉質で、ヨウ素は甲状腺の働きに大きく関連する成分として知られています。有名な温泉地は、新屋温泉(秋田県)、新津温泉(新潟県)、白子温泉(千葉県)などがあります。
効能としては、飲用では、高コレステロール血症に良いとされています。
硫黄泉

硫化水素イオン、チオ硫酸イオン、遊離硫化水素の合計が規定値以上に達した温泉です。
さらに「硫黄型」と「硫化水素型」に分けることができ、「硫化水素型」はよく「卵が腐ったようなにおい」と形容される独特のにおいを有しています。入浴する前から「ああ、温泉に来たんだなぁ」という気分になれるため、個人的には特に好きな泉質の1つで、有名な温泉地は、登別温泉(北海道)、月岡温泉(新潟県)、野沢温泉(長野県)などです。
効能としては、浴用では、アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、慢性湿疹、表皮化膿症(硫化水素型については、末梢循環障害を加える)に、飲用では、耐糖能異常(糖尿病)、高コレステロール血症に良いとされています。
放射能泉

ラジウムという放射性物質がアルファ崩壊を起こした時にできる、「ラドン」を含む温泉です。
放射性物質と聞くと怖いイメージがありますが、「ホルミシス効果」と呼ばれる免疫力上昇効果があると言われており、湯あたりしやすく刺激は強めであるものの、幅広い効能が期待できる温泉で、有名な温泉地は三朝温泉(鳥取県)、増冨ラジウム温泉(山梨県)などです。
効能としては、浴用では、高尿酸血症(痛風)、関節リウマチ、強直性脊椎炎などに効果があるとされています。
その他(泉質の名称に表示されない成分)
泉質名には表示されない含有成分として、メタケイ酸とアルミニウムについても紹介したいと思います。
メタケイ酸はケイ素と酸素からなる無機化合物で、温泉水中に自然に溶け込んでいますが、天然の保湿成分として知られ、美肌効果が期待できるとされており、由布院温泉(大分県)などが有名です。
アルミニウムを多く含む温泉は、かつては皮膚病や眼病の治療に使われており、有名な温泉は、塚原温泉(大分県)などです。
温度
環境省の鉱泉分析法指針では、温泉を地上に湧出したときの温度、または採取した時の温度により、以下の4種類に分類しています。
なお、人間が入浴して心地よいと感じる温度は、一般的に38℃から42℃の範囲であると言われています。特に41℃以上の温かいお湯を好む方が多いのではないかと思われますが、40℃弱までのお湯では副交感神経が優位に働き、リラックス効果があるとされています。
しかしながら、この狭い温度範囲におさまる温泉は、当然ながら非常に少ないのが現状で、大半の温泉施設では、加温、加水、熱交換、混泉などの方法により、適切な温度に調整されています。
もしあなたが訪れた温泉が、温度調整されておらず源泉そのままの状態であった場合、それは極めて貴重な温泉であり、大変幸運なことだと考えられます。
- 冷鉱泉:25°C未満
- 低温泉:25°C以上34°C未満
- 温泉 :34°C以上42°C未満
- 高温泉:42°C以上
pH(酸性とアルカリ性)
環境省の鉱泉分析法指針では、温泉を地上に湧出したときのpH値により、酸性、弱酸性、中性、弱アルカリ性、アルカリ性の5種類に分類しています。以下、大きく酸性の温泉とアルカリ性の温泉の2種類に分けて解説しますが、pH値が中性から大きく乖離する程、以下の特徴が強まる一方、一般的に肌や体へのトラブルにつながる可能性も大きくなるため、肌が敏感な方などは注意が必要です。
酸性の温泉
酸性の温泉は、入浴時にはピリピリした感触がある他、強い殺菌作用と抗菌力があります。火山性の温泉に多い傾向があり、泉温が高く、温泉としての特徴が強く現れている温泉が多い傾向にありますが、刺激が強いため、肌が弱い方は注意が必要です。
中でも特に酸性度が高い温泉として有名なのが玉川温泉(秋田県)で、そのpH値はなんと1.13。また、有名な草津温泉(群馬県)のpH値も約2.0です。※レモン果汁のpHが約2
ちなみに、pH3以上6未満の温泉が弱酸性温泉、pH3未満のものが酸性温泉です。
アルカリ性の温泉
アルカリ性の温泉は、泉温が低い温泉に多く、古い角質や汚れを除去し、入浴後は肌がツルツルとすることから、「美人の湯」として女性が好む傾向があります。
中でも特にアルカリ度が高い温泉として有名なのが、都幾川温泉(埼玉県)と飯山温泉(神奈川県)でそのpH値はなんと11.3。また、白馬八方温泉(長野県)も11.2と強アルカリで有名な温泉です。※洗濯用洗剤のpHが約11、石鹸のpHが約10程度
ちなみに、pH7.5以上8.5未満の温泉が弱アルカリ性温泉、pH8.5以上のものがアルカリ性温泉です。
浸透圧(成分の濃さ)
環境省の鉱泉分析法指針では、温泉の溶存物質(溶けている成分の量)により、低張性、高張性、等張性の3つに区分しています。これは、人間の体の細胞液を基準とした浸透圧による分類です。
低張性の温泉
人間の体より成分が薄く、家のお風呂やプールと同じく、水分が肌に浸透しやすい温泉です。
なお、低張性というと成分が少なく、体に優しい温泉に聞こえますが、これはあくまで人間の体と比較した場合に薄いということであり、溶存物質が温泉1kgあたり8,000mg未満であれば、低張性という判定になります。(ちなみに、一般的な家庭用入浴剤で、溶存物質がお湯1kgあたり150mgです。)
日本にある温泉の大半は低調性に該当しており、「低張性=体の負担が少ない・効能が少ない」とは必ずしも言えないため、誤解のないようお願いします。
高張性の温泉
極めて成分が濃い温泉であり、人間の体より成分が濃く、成分が体内に浸透しやすく、体の水分が出やすい温泉で、具体的には溶存物質が温泉1kgあたり10,000mg以上が該当します。その圧倒的な成分量から得られる効能が期待できる一方、水分不足になりやすく、体への負担は大きめの温泉と言えます。
全国的に希少であり、有名な温泉としては、黄金崎不老ふ死温泉(青森県)、松代温泉(長野県)などです。
等張性の温泉
人間の体と成分が同程度の温泉です。等調性を聞くと平均的な濃さの温泉だと勘違いしてしまいそうになりますが、上述のとおり、家のお風呂や多くの温泉に比べると、かなり成分量が多めの温泉になります。
湯量
温泉分析書には、「湧出量」として毎分何リットルお湯が湧出しているか記載されています。
お湯の量が多ければ多いほど、お客さんにより新鮮かつより大きくて広い浴槽を提供することが可能となります。
お湯の提供方法
循環ろ過式
湯水を消毒するなどして再利用する方式であり、消毒には一般的に塩素が使用されます。
①湯船の中の温泉水を吸入、②ろ過して不純物を除去、③消毒を実施、④温泉を湯船に戻して再利用の手順で温泉水を管理するこの方式は、少ない湯量であっても多くの人に温泉を提供できるようになる他、レジオネラ菌の発生防止など衛生面での利点があり、大型温泉施設や不特定多数が利用する大浴場でよく採用されています。
一方、時間経過による温泉の鮮度劣化や塩素の投入により温泉の薬効が損なわれるのではないかとの意見もあります。
かけ流し方式
かけ流しとは、湯水を浴槽の中に絶え間なく注ぎ続けて再利用せずに溢れさせる状態のことを言います。常に新しいお湯が注がれ、古いお湯が廃湯されることから、鮮度が高く保たれた自然に近い状態の温泉を楽しむことができ、温泉ファンの中にはかけ流し方式を好む方が多い傾向にあります。
一方、先述の循環ろ過式と比較して温泉の衛生状態を保つ難易度が高くなるとの指摘もあり、温泉施設により適切にお湯が管理されているかどうかが重要となります。
色

基本的に多くの温泉は無色透明ですが、含まれる成分によって色を持つ温泉があり、一般的に「にごり湯」と呼ばれます。視覚的に普段のお風呂と明らかに異なることから多くのファンがいると同時に、一定数苦手意識を持つ方がいます。
茶褐色(赤、金泉)
含鉄泉のように鉄分を含んだ温泉が空気に触れて酸化することでこのような色になります。塩分や炭酸を含んだ温泉にも多く、有馬温泉(兵庫県)、入之波温泉(奈良県)、千原温泉(島根県)などがこの色の温泉として有名です。
白・乳白色
硫黄泉の一部に見られる特徴であり、硫黄泉中に含まれる硫化水素が酸化する過程で生成された硫黄化合物が要因となっていると考えられています。温泉地としては、白骨温泉(長野県)などが有名です。
緑
鉄分や硫黄を多く含んだ温泉の中には緑色になる温泉があります。この色も比較的珍しく、国見温泉(岩手県)、月岡温泉(新潟県)などがこの特徴を有しています。
青
にごり湯の中でも珍しい色であり、美肌効果が期待できると言われるメタケイ酸の含有量が多い高温の温泉に見られる他、硫黄泉が光の加減で白みを帯びた青色に見えることもあります。由布院温泉(大分)や観海寺温泉(大分県)が有名です。
黒
コーラやコーヒーのような濃い色調で不透明なものから、薄茶色で透明度があるものまで様々で、フミン酸やフルボ酸などの腐植質が含まれることでこの色がつくとされています。十勝川温泉(北海道)などがこの色で有名です。
におい

温泉にはその成分により、独特のにおいを有するものがあります。上記のにごり湯と同じく、嗅覚的に普段のお風呂と違う温泉に入っていることを認識させてくれる一方、そのにおいが苦手という方もおり、温泉を特徴づける大切な要素です。
硫化水素臭(硫黄のようなにおい)
温泉のにおいといえば、最も代表的なのが、この硫化水素臭です。硫黄泉など、硫黄が含まれる温泉が主にこのにおいを有します。個人的には入る温泉がこの硫化水素臭を有していると非常にテンションがあがるのですが、硫化水素臭は「卵が腐ったようなにおい」と表現されるように、独特なにおいであるため、苦手な方もいます。
鉄のにおい
含鉄泉など、鉄分を多く含む温泉がこの特徴を有します。こちらも温泉ならではの特徴であるため、ファンがいる一方、厳密には異なるものの同じく鉄が含まれる血液の匂いを連想すると、このにおいを避ける方もおられます。
焦げたようなにおい
カルシウムを多く含む温泉は、ほのかに焦げたような独特のにおいを持つものがあります。このにおいは上記と比較すると比較的強くないにおいであり、感じ方には個人差もあるようです。
味
温泉には飲泉という用途があり、泉質の欄で記載したとおり、飲むことで得られる効能も存在します。
温泉水にはその成分により、水道水やミネラルウォーターとは異なる味を有するものがあり、「味」も温泉を特徴づける要素の1つと言えると思いますが、味については成分量や複数の成分の組み合わせによる変化が大きく、また、表現が難しい独特なものも多いことから、代表的かつ特徴的な味に限り記載します。
なお、衛生面の観点から、飲泉をする際は必ず飲泉可能である旨が明記された源泉を飲むようにしてください。また、飲む量や頻度、個々人の体調や年齢によっては健康にマイナスの影響が生じることもあるため、泉質別の禁忌や温泉管理者の注意書きに注意し、医師の指導を受けるなど、適切に利用するようお願いします。
塩味
塩化物泉によく現れる味です。なお、カルシウムが多いと苦みが強くなり、ナトリウムを多く含むと甘塩味が強くなると言われています。
鉄のような味
含鉄泉など、鉄を多く含む温泉に現れる味です。含鉄泉は飲用の効能に、鉄欠乏性貧血が認められていますが、味としては美味しいと感じる方は少数派だと思われます。
酸味
酸性の温泉は基本的に酸味を有しています。レモン汁から果実っぽさを抜いたような味であり、これも美味しいと感じる方は少数派だと思われます。
薬味
炭酸水素塩泉、硫酸塩泉、含よう素泉などの独特で複雑な味は、薬味と表現することがあります。


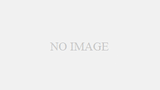

コメント